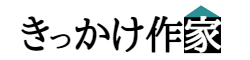『暗いところで待ち合わせ』 乙一
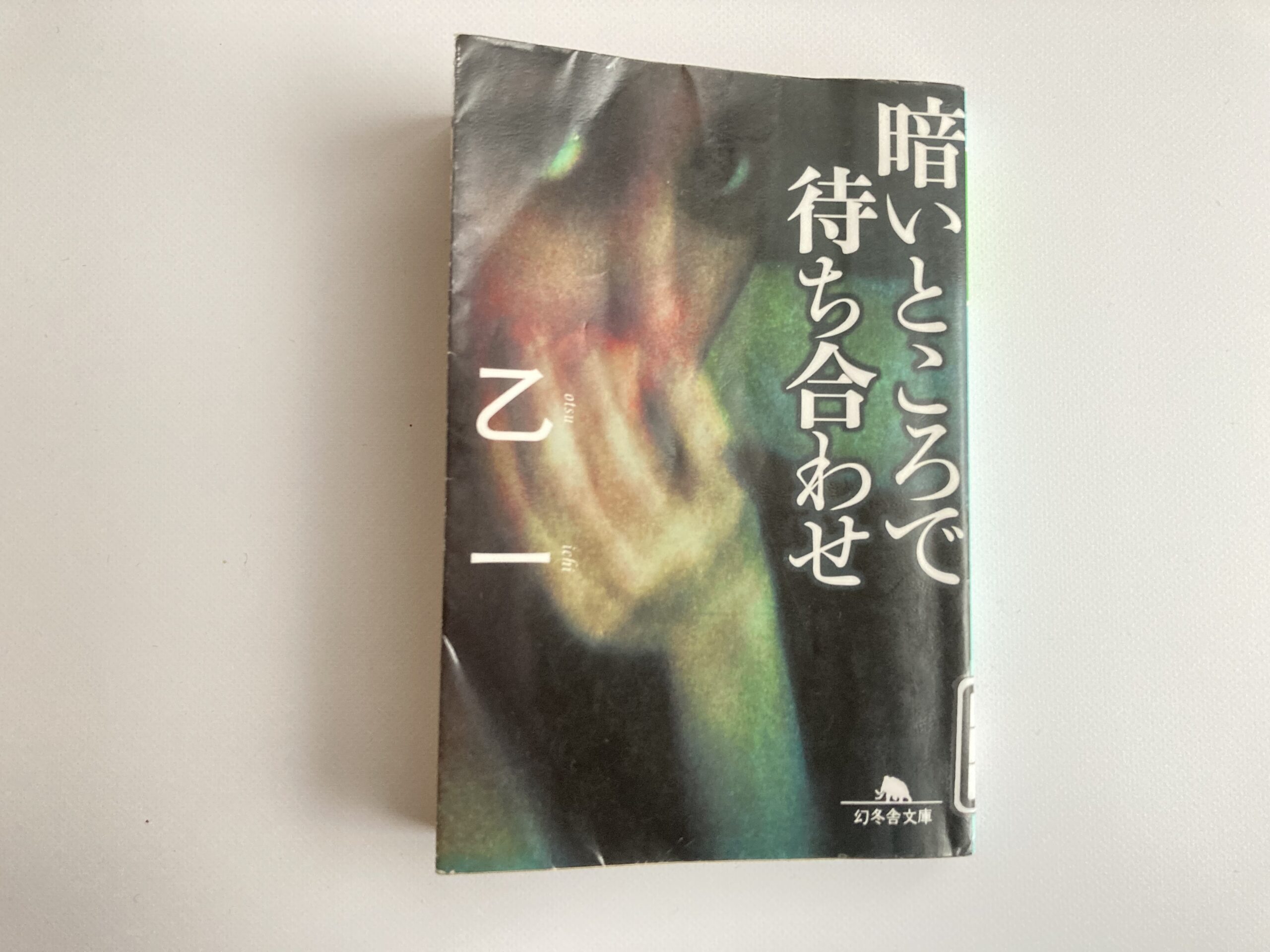
カズエは自分と違って、エネルギーを持っている気がするのだ。柔軟にいろいろなこととつきあって、彼女は世界と融合し親しく溶け合っているように思える。
例えば少し前、カズエはバイト先の知人との飲み会について話をしていた。ごく自然に、生活の一部でもあるようにだ。
一方で自分は、そういったことに関わったことがない。目が見えていて。そういう機会があったとしても、参加するのに抵抗があると思う。みんなで楽しく盛り上がっている場所よりも、静香に盛り下がっている場所のほうが、心地よさそうだった。そう考えるとき、自分は世界という名前のシチューの中で、溶けずに残った固形スープのようだと感じる。
自分とカズエの間にそういった体温の差みたいなものがあるから、彼女の話を聞いて、それがたんなる愚痴であったとしても、別世界のことのように思えて楽しいのだと思う。
これまで自分は、人との接触を避けるようにして生きていた。会社の同僚たちとも、クラスメイトたちとも心を通わせなかった。心のどこかでは、まわりで群れているものたちを軽蔑していた。そのくせに孤立して攻撃されると、深く傷つくのだ。
本当はおそらく、みんなにあこがれていたのだろう。印刷会社の喫煙所や、学校の教室で、自分も周囲の人間と同じように明るく声をかけあっていられたならよかった。
まわりで群れている者たちに対して抱いた軽蔑は、仲間に加わるのを諦めるため、そしてあこがれを抱かないための選択だったように思う。だからといって話を避けていても、悲しいことしかないというのに、そうやって身を守るしかできずにいたのだ。
会社でも、教室でも、どこにいても自分のいていい場所はここではないという気持ちがしていた。居心地が悪く、緊張し、息のつまる思いを常に味わっていた。
会社に辞表を提出したとき、自分にはためらいがなかった。別れ難い友人も、忘れ難い思い出も、何も会社にはない。その場所に自分という人間がいたというどんな痕跡も残していなかったのだ。それが悲劇であることなど、以前は考えもしなかっただろう。しかし今は違う。